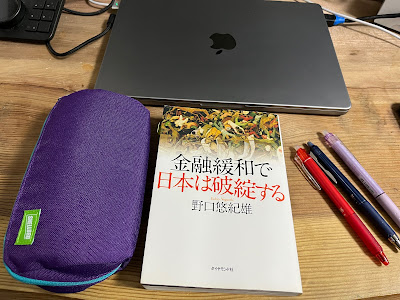特に日本とアメリカの経済的情勢について考える時、どうしても基本に立ち返るというか、その頃の両国の関係というものを振り返ってみる必要があるように思うが、その時点が「プラザ合意」ではないかと思っている。
1985年9月22日、先進5カ国の財務大臣などがN.Y.のプラザ・ホテルに集まり協議して「為替レート安定化に関する合意」を決めた。この年まだお前は生まれてなかったけど、私が31歳で、今日誕生日を迎えた母は58歳だった。
写真は、wikipedia から。最近少しだけwikiに応援カンパしました。そして当時中曽根内閣で蔵相(財務省は大蔵省)だった61歳の竹下登は、前日澄田日銀総裁らと成田を飛び立った。午前中にゴルフをしており、そのままの格好で(記者を撒くために)パンナム機に乗り込んでいる。ちょうど安倍晋三外相が国連総会のため同じ日にニューヨークに飛び立っていた。当時の日本の対米貿易黒字は400億ドル以上あった。レーガン政権のアメリカは当時「双子の赤字」(貿易赤字と財政赤字)に苛まれていたから、このプラザ会議は特に日本に対して、ヨーロッパではドイツに対して減税と金利引き下げ(→内需拡大)を要求していた。つまり分かりやすく言えば車や家電を国内で売ってアメリカには輸出しないで下さいねということである。この急先鋒に立っていたのが米財務省のベーカーであった。ただこの男お構い無しで行く先々で言いたい放題言い、それがそのまま市場の動向に反映するという有様だった。トランプがよく口にしていたAmerica first の方針は当時と全く変わっていない。翻訳すれば自分ファーストと同じである。都民ファースト、同じく。竹下はじめ大蔵省側6名と出向組等3名、日銀側4名がいた。しかし敗戦国日本の弱腰外交というものはアメリカには見透かされていたと言ってよく、ドイツの中央銀行であるブンデスバンク(マルクはECの基軸通貨)はギリギリまで自国の主張を貫いていた。そしてベーカーはじめ米財務省はFRBとは違いを見せて、政治家としての強気の姿勢でアメリカの弱体化した経済状況を何とか優位に持ち込もうとしていたのだった。
1987年10月19日の月曜日、ニューヨーク証券取引所では一斉の株売りが出て、508ドルという史上最大の下げ幅を記録した。翌日の日本でも日経平均が3836円の史上最大の下落となった。(ブラック・マンデー)これはベーカー発言により市場が3国の協調体制が崩れたと見てドルが暴落する不安に怯えたものと言われている。
同年10月29日、日銀は短期金融市場で2千億円もの買いオペを実施して資金を供給し、実質金利を下げた。(1ドル=137円台)
《ベーカー発言》
⚪︎1986年2月18日「さらにドルが下がったとしても、そう困らない」→1ドル=180円を割る。
⚪︎ 1987年3月22日「ドル相場の目標は定めていない」→ドル下落と市場は見て1ドル=148円にドルは下げた。
⚪︎ 同年4月9日、IMF暫定委員会「為替相場のこれまでの変化は、基本的に秩序あるものだった。それは巨額の貿易不均衡の減少に役立つと言える」→翌日、1ドル=142円へと急落。
⚪︎ 同年11月4日、通信社のインタビュー「アメリカの金融緩和策を変更してまで、ドル相場を維持するつもりはない」→事実上のドル安容認と受け取られて、11月6日1ドル=134円に突入。
《ドル・円を巡る動き》
1985年11月7日 日銀は短期金利の高め誘導を行った結果、1ドル=202円となった。
※1ドル=200円で輸出13業種が赤字になると言われ、190円を超えると、自動車、コンピューター業界まで赤字になると言われていた。
1985年11月13日(財務省高官)1ドル=190円になれば対米黒字が170億ドル減ると予測している。
市場は、翌年1月23日竹下蔵相が「1ドル190円になっても大丈夫か、個々によっても違いはあるが、それを受け入れる環境ぐらいはある」と述べたことが伝わり、市場では1ドル=201円から198円まで落ちた。その後195円となり、2月に入り190円を割る。そして2月中頃には180円を割ってしまう。
1986年3月17日1ドル=175円40銭と円が戦後最高値を記録。日独が協調利下げをしたものの、それを嘲笑うかのようにドルは売られ急落する。
1987年12月15日 市場は、アメリカがドルの維持に関心がないと見透かして、1ドル=127円台に落ちていく。
1ドル=137円19銭(2023年5月17日現在)
現在G7広島サミットが5月19日から3日間行われるため要人が日本に向かっているが、既に新潟では財務大臣・中央銀行総裁会議が行われた。プラザ合意後のベネチア・サミット(1987年6月7日開催)では、G7を定期的に開催することや、年初において各国の成長率、内需、為替レートなどの経済指標に基づく政策の見通しを示すことが決められた。結果的に見れば、アメリカが推し進めてきた円高:ドル安の政策は成功したかのように見えたが、威勢よく世界の主導となって推進していくはずの基軸ドルが弱くなっていき、強い円を背景に敗戦国日本がそれに変わって発言力を増していくのである。
出典;野口均「日米通貨交渉2000日」