アベノミクスを押し拡げてきた黒田日銀は、0金利政策という金融緩和を続けてきた。松田日銀に変わっても、しばらくはこの政策を維持する見通しだ。
前回で政府又は日銀が為替介入する「不胎化」介入の話をしたけれど、これは殆ど政府の外国為替資金特別会計 でドルなど外貨建て資産を購入する建前になっている。
2003年に政府・日銀による35兆円を超える大規模な為替介入(=不胎化)を行なったことによって為替レートは2005年から1ドル=120円の円安に転じ、輸出が増大し(税収が増えた)物価下落も歯止めがかかったことになった。逆に輸入物価は上昇することになる。関連企業はこの時利益を圧縮することもあるが、賃金カットをすることで凌ぐ方法を取ることもある。20年も経っているが、当時の経済情勢と今と実はそんなに変わっていないのではないか。どうしてなんだろうか?chatGPTなら為政者に都合の良い施策を提供してくれるのだろうか?
最近の日本で物価は上がっても中々賃金が上がらない、だから結局消費者の購買力に結びつかないという議論がよく行われる。確かアベノミクスではデフレ脱却を叫んでいたと思うが、消費者にとっては物価は安いに越したことはない。スーパーに行けば、野菜や生鮮食料などが次第に高くなっていく。これは原油高やウクライナ侵攻による原料の値上げ(小麦粉やバターなど)やそれに伴う中国の買い占めその他別の要因もあるだろうけど、家計が物価高に喘ぐのは共通の消費者意識だろう。
日本が0金利政策を採っている時に、海の向こうでは金融引き締め政策により高金利を続けてきた。そのことが相次ぐ銀行倒産になっているが、それでも今回のFRBは金利を上げた。
私もドラマが好きだし吸血鬼の女性と結婚したらどうなるだろうかと気を揉むけれど、いつまでも何も考えず馬鹿でいられる訳でもない。
野口悠紀雄氏は本の中で説く。「インフレターゲットとは、インフレを起こすための政策ではなく、物価が上昇し過ぎないように金融政策でコントロールする」という政策である、と。日本の場合、イギリスなどと違い「物価の引き上げ」が目標とされている。だから、いくら金融緩和をしても物価を引き上げることはできない、実現不可能な目標を設定していることになる、と。FRBの元議長ベン・バーナンキはこのインフレターゲット論者だった。彼はヘリマネ(ヘリコプターからマネーをばら撒くこと)を推奨したと思う。しかし野口氏は、この「ヘリコプターマネー」の有効性を、それを拾った人が使ってこそ意味があり、貯金してしまえば意味がない。(最近⚪︎⚪︎payが支払いが流行っているが、それか地域振興券にすれば意味があると思うけど)それより政府が公共投資などに直接投資する方が効果があると主張する。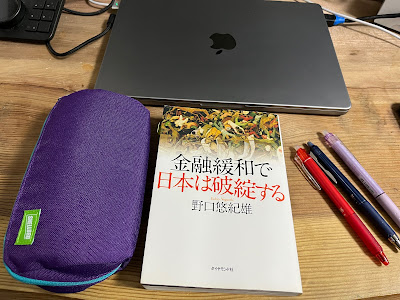
0 件のコメント:
コメントを投稿